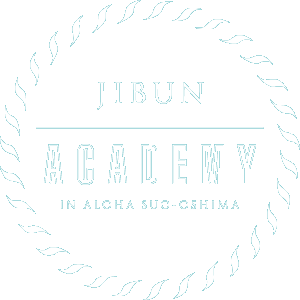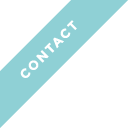広島大学が主幹となる、中国四国地域からイノベーションを創出するPSI(Peace & Science Innovation Ecosystem)から依頼をいただき、昨年度(2024年10月12日)に引き続き、今年度も安田女子中学校様(3年生149名)にてアントレプレナーシップ講演をさせていただきました。PSI公式Webサイトでも紹介していただいています。
昨年度の講演でも感じましたが、安田女子中学校様の先生方からは強いアントレプレナーシップが感じられます。ここでの「アントレプレナーシップ」とは、「自ら問いを立てて主体的に行動し、社会や自分自身に変化を起こしていく力」と定義しています。また、文部科学省は「アントレプレナーシップ教育」を「自ら社会課題を発見し、その解決にチャレンジしたり、他者と協力して解決策を探求したりする知識・能力・態度を育てる教育」と定義しています。
講演会は、45分×2コマの授業として行われました。1コマ目は、会場全体を巻き込みながらの双方向型の講話を実施。2コマ目は、代表生徒4名を中心としたパネルディスカッション形式で、1コマ目の講話を深掘りしたディスカッションを展開しました。
講話の冒頭では、授業の心得として「KYであれ」と説きました。KYとは否定的な意味の「空気が読めない」ではなく、あえて空気を「読まない人」とポジティブに定義しています。講演のような多くの人がいる場では、周囲を気にせず積極的に発言や質問をしてほしいという想いを込めて、このような言葉を選びました。
講話のテーマは「起業育〜自分の技を育てる〜」です。生徒たちは起業を特別で難しいものと捉えがちですが、「起業とは自分の技で稼ぐことである」と伝えることで、そのハードルを下げることを目指しました。どの職業でも、自分の持つ技術を提供し、対価を得ており、その本質は変わらないと伝えました。職業の差異はあっても、技術を磨き、その技術で価値を提供し対価を得るという構造は共通しており、誰でも起業家になれる可能性があることを強調しました。
具体的に自分の技を磨く方法として、「挑む→しくじる→できる」という「起業育サイクル」を紹介しました。私自身のしくじりエピソードとして、新卒で入社した会社をわずか3ヶ月で辞めたこと、2社目でもわずか2年で実質的にクビになった経験、2013年3月末時点では収入がゼロになったからこそ起業したこと、さらには起業後の3年間はアルバイト程度の収入しかなかったこと、そして起業から10年で会社員の平均年収の5倍程度になることが出来たという体験、そしてプロスポーツ選手のように、億単位の収入を得られる起業家になることを生々しく共有しました。こうしたリアルな失敗体験と成功体験が、生徒たちの共感を呼び、チャレンジ精神の重要性を伝える良いきっかけになったと感じています。
2コマ目のパネルディスカッションでは、生徒自身が考えた以下の起業アイデアが発表されました。
- 医療派遣会社
- ファッション×日本文化
- 化粧品の成分を研究する会社
- 商業施設での起業
特に「ファッション×日本文化」を発表した生徒の家庭は会社経営をされており、日常的にお父様と起業や経営について意見交換をしているとのことで、その積極的な姿勢に感銘を受けました。
講演会後の生徒アンケートの結果は、「大変満足できた」63%(95名)、「満足できた」34%(52名)という結果になり、97%の生徒がポジティブな評価を示しています。その回答理由から、いくつかを紹介します。
「挑む、しくじる、できるのサイクルは起業する人だけでなく、普段生活する上でもとても大切だなと思った。」
「とても興味深かったです。」
「わかりやすい、かつ、あれほど引き込まれる講演は初めてだった。」
「進路をまだ悩んでいるので考えるヒントになった。」
「とても先生が元気で気楽にできた。」
「楽しかったし、話を聞いててタメになった。」
「起業家のことをたくさん知れたし楽しかった。」
「講演会の雰囲気が楽しくて満足だった。」
「自信を持つことや、今を楽しむことはとても大切だなと思った。」
「すごくフレンドリーな方で2時間もあった講演が30分くらいに感じるくらい楽しかった。」
「起業のことを楽しく学ぶことができた。」
「空気を読まない(KY)という斬新な考え方を学べて、すごいなと思った。」
「とてもリアルで、失敗もあるという言葉にとても感動しました。」
一方、「所々自慢話のように聞こえてしまった」という指摘もありました。この意見は真摯に受け止め、次回は自慢と受け取られる表現を控え、生徒がさらに共感しやすい内容を目指します。
今回の講演を通じて改めて感じたのは、安田女子中学校の先生方の“起業家的マインド”です。アントレプレナーシップ教育の重要性が叫ばれる中、同校では生徒一人ひとりが地域や社会の課題に目を向け、解決策を探究する力を育むことを大切にしていると強く感じました。
安田女子中学校のみなさま、そしてPSIのみなさまに感謝するとともに、これからも「挑む・しくじる・できる」を繰り返しながら、私自身も新たなステージに挑戦していきます。